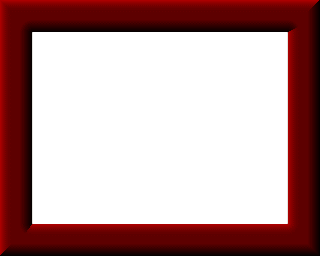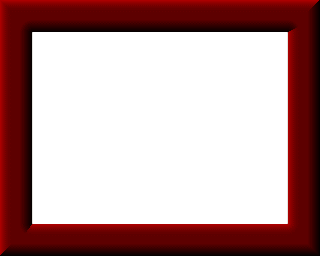正月の富士山
★富士の頂角、広重の富士は八十五度、文晁の富士も八十四度くらゐ、・・・・広重、文晁に限らず、たいていの絵の富士は、鋭角である。いただきが、細く、高く、華奢である。北斎にいたつては、その頂角、ほとんど三十度くらゐ、エッフェル鉄塔のような富士をさえへ描いている。けれども、実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百二十四度、南北は百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。 ・・・・太宰治の「富嶽百景」の書き出しである。
★戌年の年明けは静かに幕あけであった。「本栖湖に映る初日の出のダイヤモンド富士」のTV画面を妻がデジカメに納めた。元旦8時前後の映像は素晴らしい。5日の朝はスカイツリーや伊豆からの澄みわたる空から、雪を被った富士山のTV画面もみた。担当者の初仕事だったのだろう。
★若い頃に浮世絵師の富士山は、どうして鋭角かと思い、「富嶽百景」の小説に出会い、同じ思う人いるのだいう事を思いだし、正月に3度目の読み返しをした。小説の中では富士山のみえる山に登り、見た富士は想像より高いとある。絵師もそんな経験をした為かもしれない。
★初夢で縁起が良いとされる「一富士、二鷹、三茄子 」の意味が分からずにきた。辞典で調べたら特段の意味はなく、由来として駿河の国の名物をうたったものという。続いて「・・・四扇,、五煙草、六座頭」だそうである。正月番組表に「座頭市」の掲載が多い。こんなところがヒントんなのだろうか。 |